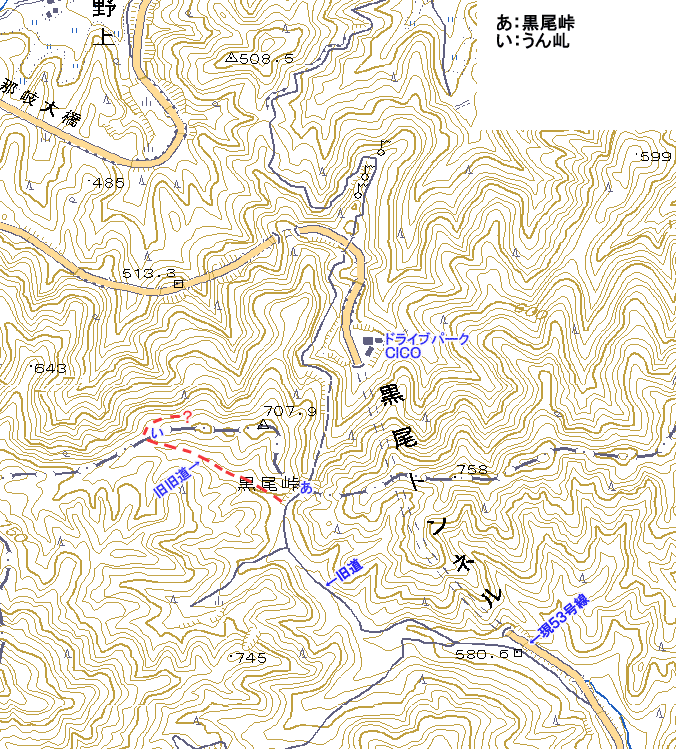さきほどの黒尾峠のレポートはネット上に数多くあるが、これから行こうとする
旧旧道のレポートはほとんど無いに等しい。そもそもそんな峠があることを知っている人が
皆無なのだ。どんな峠かわくわくする。
新道がほんとうに明治11年から造られたとすると、それ以前はこの道を多くの旅人、牛馬が
歩いていたこととなる。そういう光景を想像しながら歩くのが廃道マニアの楽しみの一つ。
ほとんど登りらしい登りもなく峠に着く。
 |
| うん乢という名前だそうです |
|---|
ここも黒尾峠と言うのか帰宅後調べてみるとここは『うん乢』というのが正式名だった。
そして、このうん乢にはでかい石仏がある。中上さんと比べてもわかるように相当でかい。
しかも表面に傷みがない。
ふつうならもっとじっくりと石仏を眺めているのだが、ちょっと興奮気味で
写真もそれほど撮っていないのがあとでわかった。巨大地蔵の右手にある小さな地蔵
(よその峠ではこれぐらいのが置かれているのだが・・・)の年号も写真写りが
悪くて確定できず(たぶん文化か?)。
 |
| 説明板と小さめの地蔵もある |
|---|
文化12年に書かれた『東作誌』にはこの峠のことが書かれていた。
『因州界なり。三十三町三十間、自然の上り坂にして絶頂に至り弧木一本、
石地蔵一躯あり、是即ち作因及陰陽両道とす』
あれ?石仏は二体じゃないの?って思ったのだが、巨大地蔵は文政七(1824)年の銘がある。
つまり『東作誌』の書かれた頃には無かったのだ。横の小さな地蔵がそれだったのかも。
 |
| 説明板を読む中上さん |
|---|
由来を書かれた看板はもうボロボロになっていて読めない箇所もある。
読めるところを抜粋するとこうある。
『この街道は津山備前往来として通行の盛んな峠であった。
文政五年頃因幡に伝染病が□□旅人も村人も薬は無し非上(そのまま)に苦労したので□□
安全と村人の無病息災を祈願して石地蔵を建□□。運搬するのには大変な労力が必要なので
特別製の大□□を造りモウソウ竹をコロに敷き、麻とカズラを使って太い□□三本造り、
曳き上げた。土師の郷、十日市村から奥の十四ヶ村、約百五十名が惣事で出勤した。
奥早野と栃本の女性は惣出で炊事にあたり、炊き出しのむすび、お茶、酒等を負い上て賄い
(昼晩の二食付き)をした。七日目にやっと安置できたと古文書に記されてあります』
建立に当たった村役人の項を読むと、奥早野村、栃本村、西宇塚村(三村は鳥取)。それと馬桑村(これは
岡山)四村が記載されていた。前述の文章からすると、どうも鳥取側から担ぎ上げたように想像できる。
それと文政五年の伝染病とは世界的パンデミックの余波が日本にも及んだコレラ(後に文政コレラと名付けられた)
を指していると思う。
 |
| もう一体、首無し地蔵もある |
|---|
この峠は広い削平地があり、巨大地蔵は西の端にある。そして東の端には首無し地蔵があった。
このあいだにはどんな建物があったのだろうか?いわゆる関所のようなものかなあ・・・。
 |
| ここはMTBで下れる? |
|---|
さて、問題は鳥取側へ下っている道の状態だ。見るときれいだし、地籍調査かなにかの赤いプラ杭が
あったりするのでひょっとすると下界まで極楽シングルトラックかも。
地形図にはまったく道の記載がないので極楽か地獄かは行ってみなければわからない。
それを確かめるべくMTBで下ってみよう!!
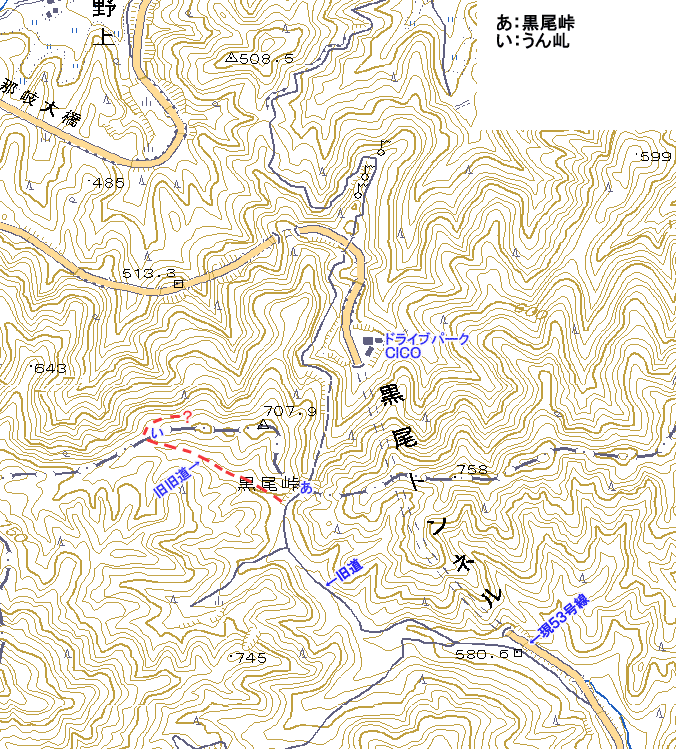 |
| 地図です |
|---|
|