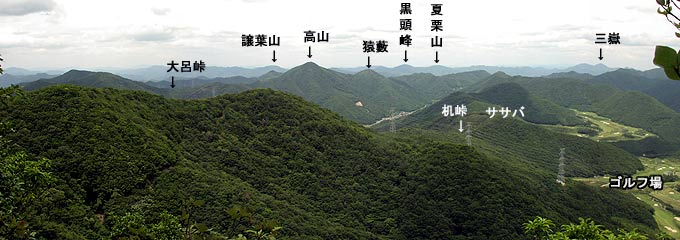|
西光寺山はいろんなコースで登り、そして下りましたが、寺坂コースだけはまだ歩いたことがありません。
山頂に行くだけなら短時間で行けるでしょうから、山頂ではゆっくりとオカリナを楽しんで、
下山はいつものように登山道でないコース(こういった道を総称して『やまあそコース』と呼んでます)で下ってみます。
篠山市今田町本荘の七星ソースの社屋奥を進んでいきます。墓地に車を止めるのが手っ取り早いですが 足元のしっかりした車なら林道の終点まで行けます。適当なのはため池の堰堤近くあたり (頂上まで約2.1kmの標識あり)でしょうか。そこへ車を止めて8時40分スタート。いきなりですが サギソウの咲く湿地帯に寄り道します。 8月頃が見頃なので何にも咲いていないように見えますが、この時期はモウセンゴケの白く小さな花が 咲いています。デジカメで写そうとしますがこれがむずかし〜い!
東屋が見えてきました。右手にはわかりにくいですけど石灯籠もあります。ここを直進すると 炭焼き窯横を通過して登っていくメジャールート。左手の草に覆われた細い道には 『寺坂登山道(寺屋敷跡)』と標識があります。東屋には『西光寺山の金の鶏』民話の 大きな看板が取り付けられていますがここに全文をコピーしているとたいへんな字数なので割愛! 寺坂コースは入口だけ草むしていて入るとそうでもありません。木製の祠跡、新しい石の祠、そして石組みで出来た 祠と三基の小さな祠がありました。石組みの祠の中には四角形の石が祀られています。何かの石塔の一部 のようです。表面にうっすらと文字が彫られていますが薬師如来を表す梵字『バイ』のようです。 小さな流れを渡ると左に行かないように気を付けましょう。平行するように廃道となった林道が左手にあり、 ともすればそちらに行ってしまいそうになります。植林の中の細い道には『本堂跡山頂至』と書かれたブリキ板が 転がっていてこちらが正規ルートです。不明瞭な踏み跡しか残っていないのでは?と想像していたがまったくその心配はない。 蜘蛛の巣もほとんどない気持ちの良い道です。やがて細い谷川を横切ると小さくガレた急斜面を登っていくことになる。 いくつも炭焼き窯跡が残っています。昔はこの谷斜面で多くの炭焼きの煙が立ち上っていたのでしょう。 周囲には山桜、ウバメガシ、コナラ等が多く目に付く。汗はかくものの下から吹き上げてくる 冷風のおかげで蒸し暑いといった感じはない。どこが寺跡かわからないので とにかく登っていく。やがて社町と篠山市の境界尾根に出る。9時40分。
尾根は展望はないがさらに快適な道となっている。尾根の真上に道はなく、進行方向左下に 平行して続いている。寺跡がこの奥にあるとしたら結構な標高だと思う。 だとしたら水場が必要だがこれほどの標高であるのでしょうか?? そんなことを思いながら歩いていると大きな岩が現れ始める。 おっ〜!なんだか怪しげな場所だぞぅ・・・。 おお!こんな所にチョロチョロながらも水が流れてるやん!!その水をたどって行くと 大岩が点在する中にフラットな敷地跡らしき所がある。古いブリキの看板がぶら下がっていて それには『古井戸跡』、『寺屋敷跡』などと書かれていた。しかし寺跡はここだけではなかった。 |